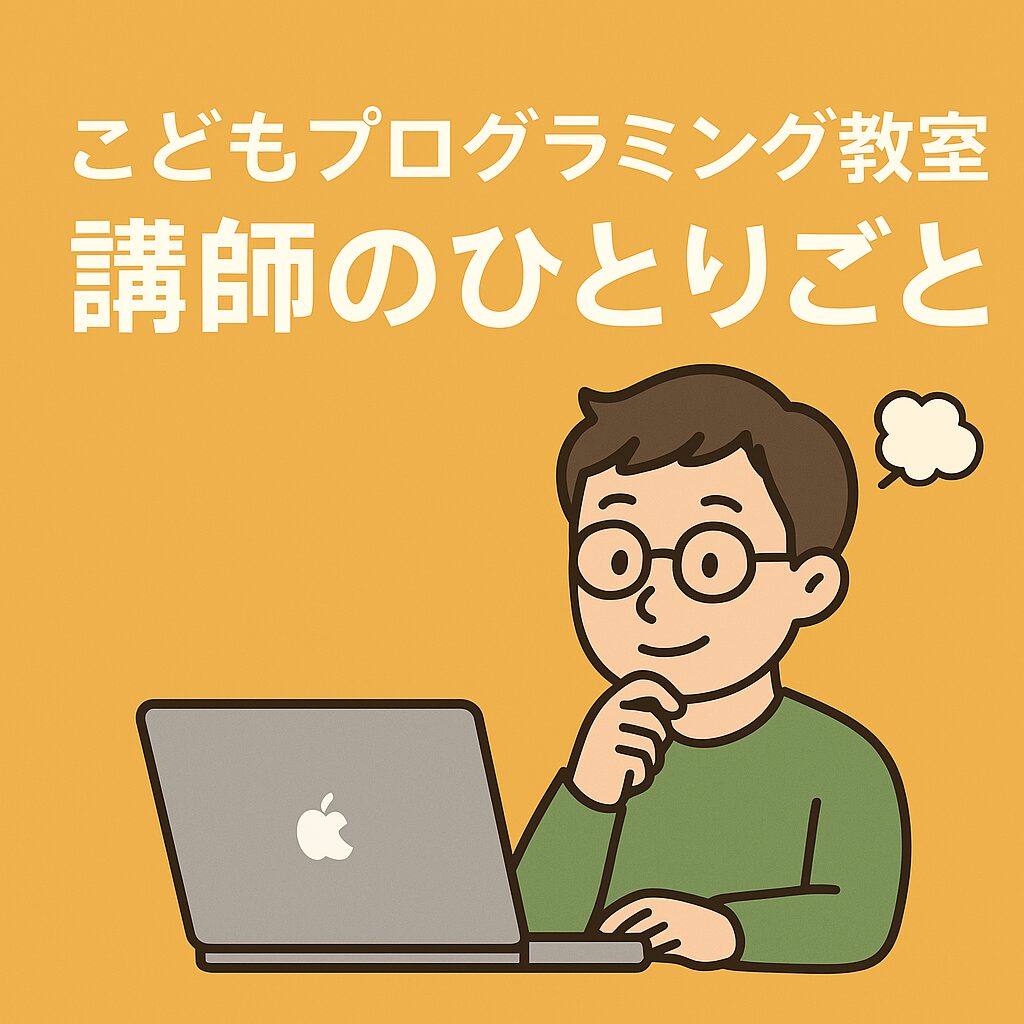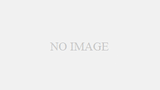こどもプログラミング教室講師のひとりごと
こんにちは。「ぱそんこ」講師のシンザトです。
SEO対策も兼ねて、気まぐれなペースにはなりますが「講師のひとりごと」という形でブログを書いていくことにしました。日々の教室の様子や、思うことをゆるりと綴っていきたいと思います。
※この記事では添付画像にAIを使用しています。画像内に文字化けなどがあることもあります。
ぱそんこという名前について

「ぱそんこ」という名前、少し変わっていると思いませんか?
これは実は「パソコン」とタイピングしようとしたときの“誤入力”が由来なんです。
キーボードを打っていて、うっかりミスってしまうことってありますよね。そんな小さなミスから生まれた「ぱそんこ」という響きが、どこか愛らしく、そして子どもに寄り添う教室でありたいという想いにもぴったりだと思い、この名前に決めました。
…ただ正直に言うと、生徒から「ちょっと恥ずかしい…」なんて言われたこともあります(笑)。でも、横文字や難しい漢字の名前よりも、覚えやすくて親しみやすいかなと、今もこの名前で続けています。
教室スタートから5年が経ちました
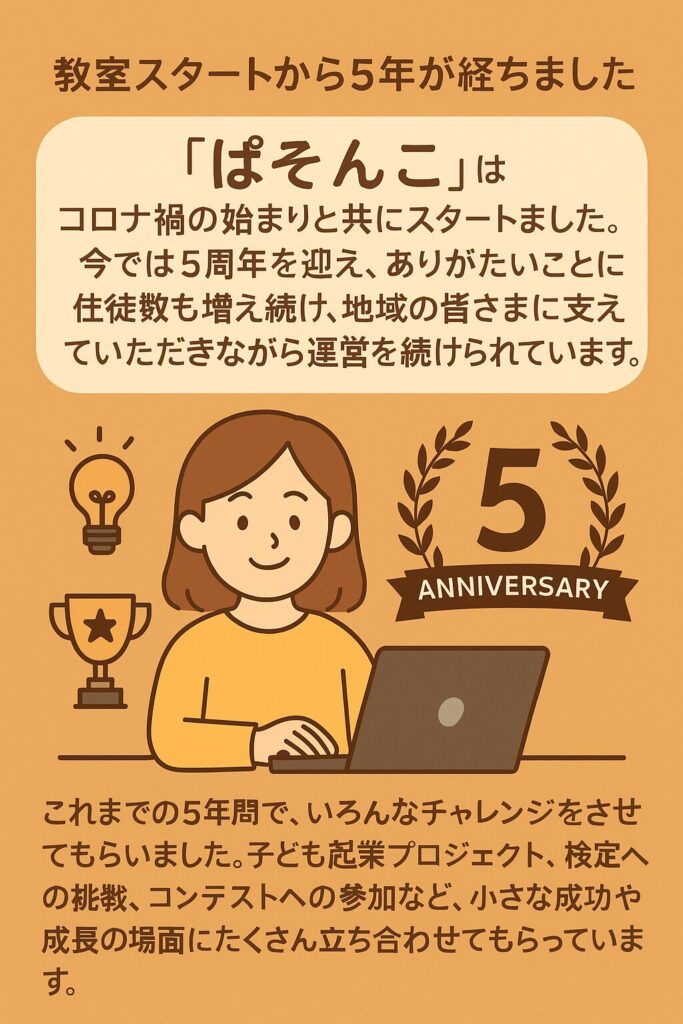
「ぱそんこ」はコロナ禍の始まりと共にスタートしました。今では5周年を迎え、ありがたいことに生徒数も増え続け、地域の皆さまに支えていただきながら運営を続けられています。
これまでの5年間で、いろんなチャレンジをさせてもらいました。子ども起業プロジェクト、検定への挑戦、コンテストへの参加など、小さな成功や成長の場面にたくさん立ち会わせてもらっています。
「プログラミング教育」という言葉が少し落ち着いてきた今だからこそ、改めて子どもたち一人ひとりの“生きる力”を育てる場として、この教室の役割を考え直しています。
本当はもっと広く、地域に根ざした活動をしたかった

開業当初は、「旭川」だけでなく、「士別」「留萌」「深川」「上川」などの地域で出張授業をすることを計画していました。
少子化が進む中、旭川だけでなく他地域にも学びの場を提供できればと思っていたからです。
また、ICTスキルやパソコンリテラシーの地域格差は思った以上に深刻です。だからこそ「子どもたちにとって当たり前にパソコンが使える環境」を、どこに住んでいても整えてあげたいという気持ちは、今でもずっと持ち続けています。
できることなら、こういった出張授業の費用を町内会や自治体が負担し、子どもたちは“無料”で学べる形になったら素敵だなと思っています。
実はその想いもあって、開業当初から「非営利活動法人」の設立を考えていました。今もその夢は変わらず持ち続けていて、少しずつですが準備を進めています。
もしこの記事を読んで、「運営に関わってみたい」「理事や役員として関わってもいいかも」と思ってくださる方がいらっしゃったら、お気軽にご連絡いただけたら嬉しいです^^
教育現場の現状について思うこと
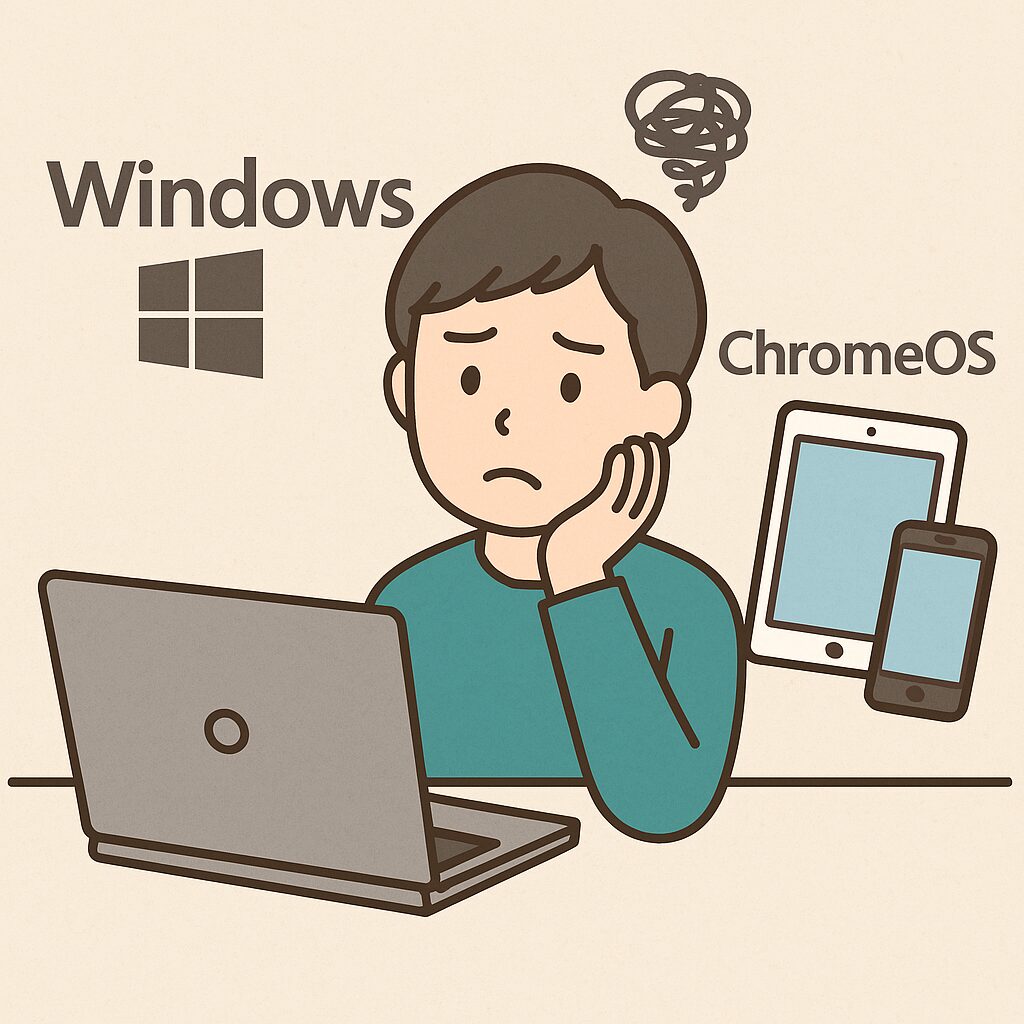
私が少し心配しているのは、今の教育現場での「ICTの使われ方」です。
たとえば、パソコンを使う社会人の多くはWindowsOSを使っていますが、旭川の学校教育現場ではiPadやChromeOSが主に使用されています。
もちろん、それぞれに良さがありますが、使えるソフトや操作方法は全く異なります。将来社会に出た時に必要とされるスキルが、学校で十分に身についていないというのは、やはり気になります。
最近は「スマホやタブレットは使えるけれど、パソコンは苦手…」というお子さんが本当に増えてきています。
参考:タブレットとパソコンの違いについて
以下は、Gakken教育総研の資料を元にした比較表です:
| 比較項目 | タブレット | パソコン |
|---|---|---|
| 操作方法 | タッチ操作。手書きに強いが長文には不向き。 | キーボード・マウス操作。文章作成・編集などに最適。 |
| 携帯性 | 軽量で持ち運びやすい。 | やや重いが高性能。マルチタスクにも対応。 |
| 処理能力 | 基本的な操作に十分。ただし重い処理には不向き。 | 高性能で複雑な作業に対応。ビジネスでも主流。 |
| 画面サイズ | 小さめ(8〜12インチ)。表示領域は狭め。 | 13インチ以上が主流。複数ウィンドウで作業も快適。 |
| バッテリー性能 | 長時間使えるものが多い。 | 処理能力が高い分、電池消耗も早い傾向。 |
わが家でもタブレットは時間制限中です

ちなみに、我が家でも子どもにタブレットの使用時間を制限しています。
スマホやタブレットはとても便利ですが、使いやすい分、長時間使いすぎてしまうというリスクもあります。研究などでも、依存や集中力低下についての報告があるため、適度な距離感を持って使っていけたら…と思っています。
もちろん、パソコンも無制限で良いわけではありません。ただ、パソコンは基本的に机に向かって使うものなので、どうしても“集中して取り組む時間”が生まれやすい。そういう意味でも、学びに活かしやすいツールだと感じています。
最後に
このブログでは、これからも講師として感じたことや、子どもたちの成長の様子、そしてプログラミング教育の今とこれからについて、ゆるく綴っていこうと思っています。
どうぞ気軽に読んでいただけたら嬉しいです^^
そして、地域や子どもたちの未来のために一緒にできることがあれば、ぜひご一緒させてください。